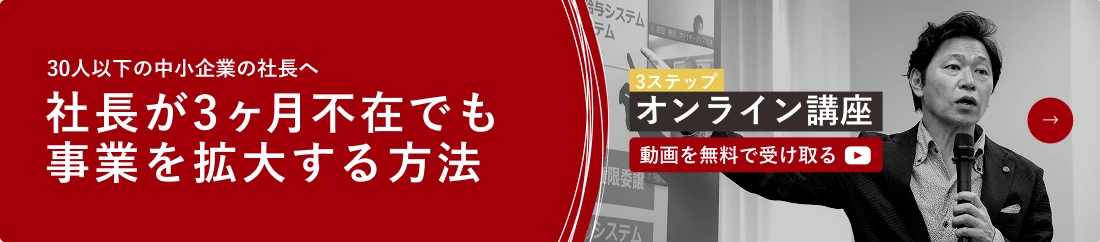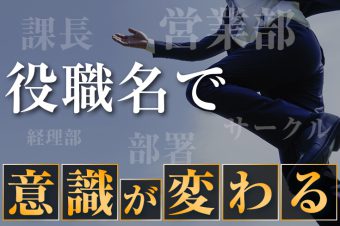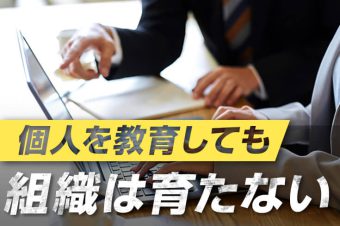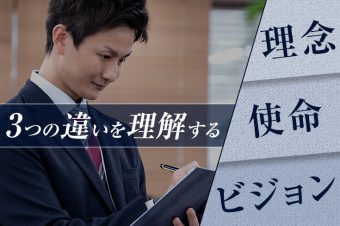- TOP
- ブログ&YouTube
- ミスが頻発する組織の原因とは


ミスが頻発する組織の原因とは
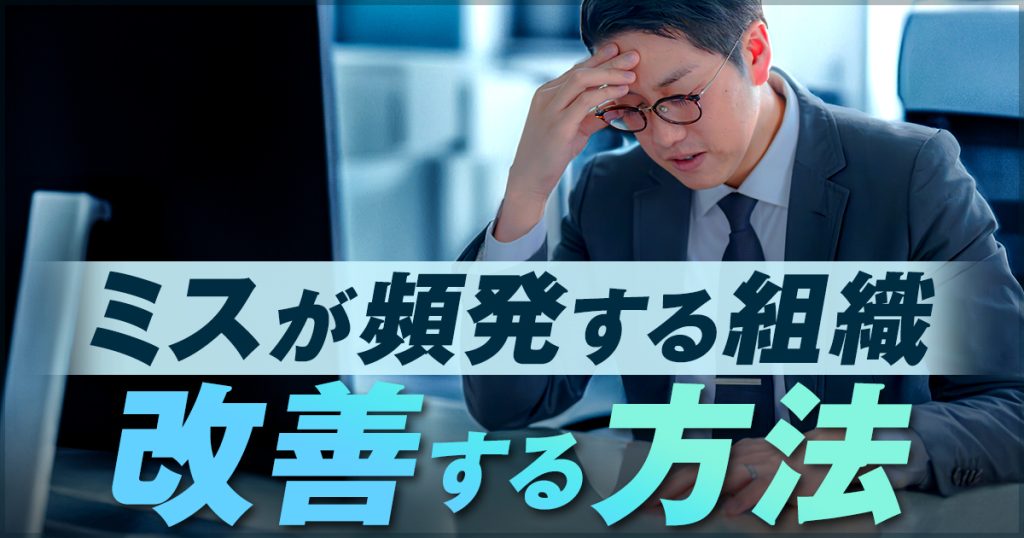
今回のテーマは「ミスが頻発する組織の原因とは」です。
先日、創業10年目を迎えるという経営者の方から、組織の現状についてご相談をいただきました。
「創業から今日まで、誠心誠意商品の開発・改善に取り組んできました。おかげさまでお客様からの信頼は厚く、会社も成長を続けています。しかし、商品に自信がある一方で組織に危機感も抱いています。お客様へのメールに誤字がある、資料発送を忘れるなど、ミスが頻発しているのです。
社員には『商品以外で信頼を落とすのはもったいない』と何度も話しているのですが……ことの重要さが伝わっていないのか、その場しのぎの反省ばかり。どうすれば社員の注意力を高め、ミスを減らしていけるでしょうか」
顧客からの厚い信頼を得ていること、本当に素晴らしいですね。それだけに、商品以外の部分にミスが多発している現状へのフラストレーションも大きいことと思います。
ご相談には「どうすれば社員の注意力を高められるか」とありますが、私は社員の注意力というよりも「組織全体の価値観」に着目して解決策を講じることをおすすめします。今回は、その理由を解説しつつ、具体的なアプローチ方法を考えていきます。
仕事への価値観が結果を分ける
社員の能力よりも組織の価値観に着目すべき理由は、ミスを繰り返す状況を根本から改善するためです。なお、ここでいう「価値観」とは”仕事への向き合い方”のことを指しています。
たとえば、ミスをした際に「やっちゃった、まあいいや」で済ませる人もいれば、「また同じミスをしないための方法を考えよう」と改善に向けて行動できる人もいますよね。これが、仕事に対する向き合い方=価値観の違いです。
社員の注意力を高めるためにいくら工夫を凝らしても、根本にある価値観が「ミスをしてもいいや」のままでは改善は望めません。反対に、「ミスを繰り返さないために行動する」価値観が当たり前になれば、経営者がお小言を言わずとも自然にミスは減っていく。つまり、現状を改善するためには、「ミスを繰り返さない価値観」や「文化」を組織に根付かせる必要があるのです。
価値観が組織に与える影響
価値観や文化というとどこか曖昧な印象がありますが、これらが組織に及ぼす影響の大きさは計り知れません。なぜなら、人は良くも悪くも易きに流れる――すなわち、多数派の声に迎合してしまうものだからです。
たとえば「ミスにいちいち真面目に向き合うのは馬鹿げている」という文化が蔓延している企業があるとします。ここにどれだけ素晴らしい人材が入ってきたとしても、その人は遅かれ早かれミスを軽視する文化に飲まれてしまうでしょう。
もちろん流されない人もゼロではありませんが、多数派の声に抗い続けられるほど強い信念を持っている人は、なかなかいないのが現実です。
反対に、常に改善のPDCAを回し続けることを賞賛する文化の会社に入ってきた人は、元々の価値観が多少緩くとも、次第に改善の文化に馴染んでいく可能性が高い。
そして、良い価値観を組織に根付かせるためには、まず経営者が理想とする価値観を明確に言語化して社内に共有し、理想と現状のギャップを埋めるための行動を起こしていく必要があるのです。
社員とともに理想の文化を築く
このようにお伝えすると、「そんなことをしたら社員が反発するのでは」と不安に感じる方もおられるかと思います。
実際に、経営者が価値観を打ち出したことがきっかけで社員が反発したり、離職したりするケースも存在します。しかし、私個人の経験ではありますが、「全員が辞める」といった極端なケースはこれまで一度も見たことがありません。
むしろ、「これでしっかり仕事ができる」と喜びの声が上がる、本当は真面目に働きたいと思っていた人がぐっと頭角を現すなど、プラスの変化が起きるケースもよく見られます。誠実に仕事に向き合うことを望む人材は、案外多いものなのです。
そして、経営者の価値観に反発する人が会社を去っていくのは、必ずしも悪いことではありません。なぜなら、価値観に賛同する社員だけが組織に残れば、経営者が一方的に押し付けることなく、社員と協力し合って強い文化の会社を築いていけるからです。
本日の結論
弊社は、会社として重んじる価値観を「コアバリュー」として共有しています。会社によっては「クレド」や「行動指針」「社訓」等と表現するところもあるでしょう。名称にかかわらず、重要なのは”どのように仕事に向き合ってほしいか、どんな価値観で働いてほしいか”という理想を明文化し、社員に向けてしっかりと共有することです。
まずは、経営者としてどんな価値観の会社を作りたいかを改めて見つめなおし、それを言葉にすることから始めてみてください。その取り組みはきっと、ミスが頻発する現状を改善するとともに、貴社の組織力をさらに強めるための重要な一歩となるはずです。