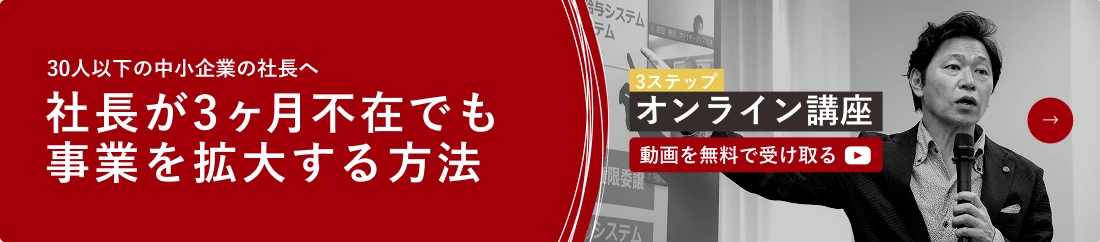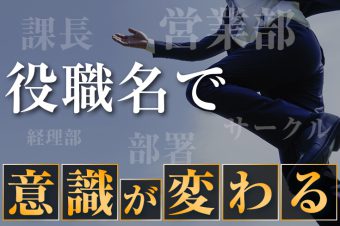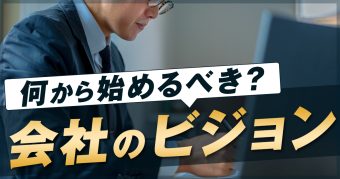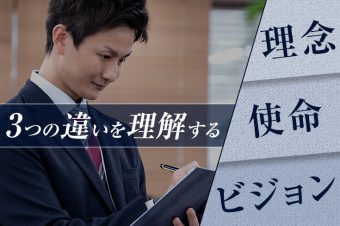- TOP
- ブログ&YouTube
- 社員の離職との向き合い方


社員の離職との向き合い方

今回のテーマは「社員の離職との向き合い方」です。先日、クライアントの方から次のようなご相談をいただきました。
「私は2代目の経営者で、社員50名程度の会社を経営しています。採用が難しい時代において、今いる社員が定着するように様々な取り組みをしています。それでも、一定数の社員は、離職していくのです。それぞれの人生があるので、会社を辞めること自体が悪いとは思わないのですが、どこかで“会社を否定されたような気持ち”になってしまいます。また、社員の離職に気持ちを引きずられたり、業務のしわ寄せで社内が混乱したりします。社員の離職とどう向き合っていけば良いのでしょうか」
理由はどうあれ、どの経営者にとっても、社員の離職はやはり寂しいものです。悔しさや安堵、反省といった様々な感情が交錯し、決して楽しい出来事とはいえません。向き合ってみると、想像以上に心を引き裂かれることもあります。そこで今回は、社員の離職に対して、私がどのように向き合っているかをお話しできればと思います。
離職率の目安
ここで少し、社員の離職率はどのくらいが適正なのか、考えてみましょう。
たとえば、誰も辞めない会社は一見良さそうに見えますが、人が入れ替わらず、新陳代謝が起きません。実際、そういった会社は、独立事業者が集まっており、それぞれが比較的自由に動いているケースも多く見られます。一方で、私たちのようにチームで仕事をしている会社は、たとえ同族同士であっても衝突が起きやすいものです。そう考えると、ある程度の人材の流動は、避けられない現実だといえるでしょう。
私自身がひとつの基準としているのは、「5年勤続のスタッフが65%残っていること」です。この数字の根拠は、日本の離婚率です。日本では、夫婦の約35%が離婚しており、裏を返せば約65%は婚姻を継続しています。「一生一緒にいる」と誓った関係でもこの数字ですから、職場であればなおさらだと思いませんか?
現在、ブレインマークスにおける5年勤続の定着率は、全体で65%。内訳を見ると、新卒は70%超、中途採用では60%といったところです。中小企業でも規模が大きくなれば、どうしても目の届かない部分が出てきます。だからこそ、まずは「5年で65%」というラインを保つこと、そして可能であれば少しずつ高めていくこと。この辺りを目安にしてみるのが現実的かもしれません。
具体的な対策
定着率を保つために、まず取り組むべきは「企業魅力を高めること」です。
社員が「この会社で働けて良かった」と心から思えるように、会社の魅力を日々積み重ねていく必要があります。
具体的には、「生産性を高め、ゆとりを持って働ける環境を整えること」「特定の社員に業務のしわ寄せがいかないように配慮すること」などが挙げられます。中でも重要なのが、マネジャーの教育です。マネジャーのレベルによって、社員の働きやすさには大きな差が生まれます。その企業の文化に合ったチームづくりを進める上でも、マネジャーの育成は欠かせません。
そして次に必要なのが、「採用の見直し」です。
夫婦の離婚理由の第一位は「性格や価値観の不一致」といわれています。同じ空間で長い時間をともに過ごす中で、価値観のズレを感じると、人はどうしても反発してしまうものです。私たち中小企業では、大企業のように転勤や部署異動によって環境を柔軟に変えることが難しいため、なおさら、価値観の一致が重要になります。
だからこそ、採用でも「一緒に働くうえで価値観が合うかどうか」をしっかり見極めることが、定着につながる重要なポイントになるのです。
PDCAを回す
企業魅力を高めるために、私がオススメしたいのは「社員満足度調査」の実施です。正直、初めて取り組んだときは、それほど必要性を感じていませんでした。しかし、継続していくうちに、会社の変化や成長を実感するようになったのです。「何がダメだと感じているのか」を見える化できれば、改善に取り組むことができます。社員満足度は、顧客満足度と同じくらい、企業経営にとって重要な指標なのです。
たとえば、弊社では「福利厚生」が課題になっていました。ワーケーションの実施、長期休暇の取得促進、確定拠出年金の導入など、さまざまな制度を整えてきたつもりでしたが、「きちんと明記し、丁寧に説明しなければ伝わらない」という学びもありました。
現在、社員満足度の全体スコアは90点ですが、福利厚生の項目は73点。来年、この数字が80点台に上がっていれば、これまでのチャレンジが社員に届き始めたというサインなのでしょう。
このように、PDCAを回しながら、働きやすい環境を経営者が率先してつくっていくこと。それこそが、良い社員に定着してもらうための、大切な土台だと感じています。
今回のまとめ
会社を経営している限り、人材の流動はつきものです。想定範囲内の離職であれば、過度に傷つく必要はありません。大切なのは、淡々と会社の改善に取り組み続けること。そうすれば、本当に必要な人材が残ってくれる環境をつくれるはずです。自信を持って、取り組んでみてくださいね。応援しています。