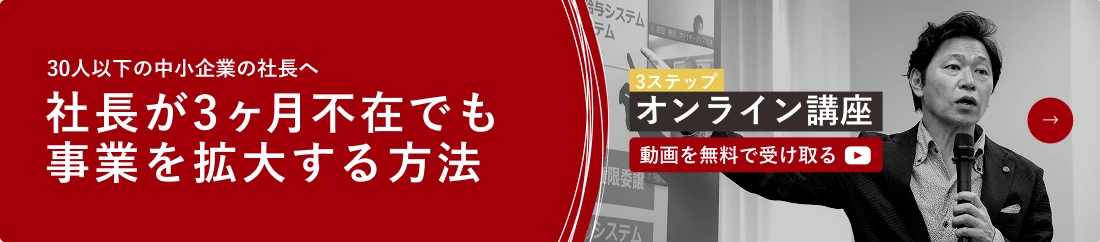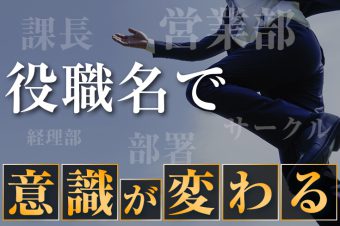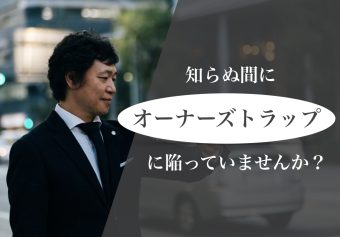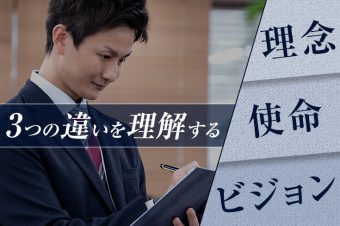- TOP
- ブログ&YouTube
- 業績が伸び悩んだときにやるべきこと


業績が伸び悩んだときにやるべきこと

今回のテーマは「業績が伸び悩んだときにやるべきこと」です。
先日、経営者の方からこんなご相談をいただきました。
「創業から10年、なんとか年商7億円を超えるところまでやってきました。しかし最近、業績の伸びが鈍化してきています。安東さんのおっしゃる『オーナーズトラップ』にハマっているからなのでしょうか……。
安東さんは、特に何かが悪いわけでもないのに業績が伸び悩んでいる会社も見てきているのではないかと思います。このような場合、何から着手していくべきなのでしょうか?」
業績が「伸び悩む」とは、”落ちている”のではなく”停滞している”ということですね。弊社のクライアントにも停滞に悩む企業は少なくありませんし、ご相談者様のように「特に何かが悪いわけではない」「思い当たる要因がなく、何をすればよいかわからない」と困っている経営者も多くおられます。
しかし、業績の停滞には必ず原因があります。そして、その原因を見つけるために着手するべきなのが、現状の徹底的な「分解」です。今回は、この「分解」の方法について詳しくお伝えしていきます。
「商品」「エリア」「プロセス」の分解
まずは、業績を「商品」「エリア」「プロセス」の3つの角度から分解していきます。
はじめに、最もスタンダードな「商品」ごとの分解です。商品の種類ごとに、売上の推移を分析してみましょう。去年までに比べて伸びが鈍化している商品や売上が落ちている商品には、必ず改善の余地があるはずです。
次に「エリア」ごとの分解です。売上が伸びている地域と停滞している地域に注目し、契約率や売れ筋商品、競合状況といった違いを分析するということですね。
たとえば「広告反響率が首都圏では低く、地方は高い」という違いを発見すれば、「広告配分を見直す」という改善案を導き出せます。このように、エリアに着目して数字を分解すると、商品ごとの分解だけでは見えなかった新たな切り口に気づけるのです。
続いて「プロセス」ごとの分解です。営業のプロセスを①集客②ナーチャリング③クロージング④リピートの四段階に分解し、どの段階に停滞があるかを見つけましょう。
たとえば、見込み顧客の数が減っている場合と、既存顧客のリピートが減っている場合とでは、取るべきアプローチが大きく変わります。また、すべての段階で成果が芳しくないという場合は、「どこから改善するのが最も効果的か」という視点で改善方法を検討することもできますね。
「営業力・商品力」の分解
さて、ここまでは主に「営業力」に関係する分解方法をお伝えしてきました。しかし、実際の原因は営業力ではなく商品力にあることも多々あります。業績停滞の原因を探すときは、先述した「商品・エリア・プロセス」の分解と併せて、ぜひ「原因が営業力にあるのか、商品力にあるのか」の分解も行ってみてください。
ライバル会社の台頭、商品のコモディティ化、より魅力的な新商品や新技術の登場……こうした要因から相対的に商品力が低下し、業績が伸び悩むことは珍しくありません。あくまで私個人の体感ではありますが、これまでに見てきた業績停滞のケースのうち、およそ半数程度は商品力に原因があったように思います。
特に、「ここまで一気に業績を伸ばしてきたのに急に停滞した」という場合は、商品の競争力低下に原因がある可能性大です。この場合は、まずエンドユーザーのニーズを見つめなおして自社商品をブラッシュアップし、そのうえで訴求方法の変更も検討していくことが、停滞の解消につながるのではないでしょうか。
本日の結論
業績が停滞してしまったら、行うべきは一にも二にも「分解」です。分解を繰り返せば原因を絞り込むことができ、原因が特定できれば有効な改善策も見えてくる。そして改善策が見つかれば、PDCAを繰り返して問題解決に近づいていけるのです。
停滞の原因が思い当たるときはもちろん、「何が悪いかわからない」と感じたときこそ、あらゆる角度から徹底的に分解を重ねてみてください。それがきっと、貴社が再び業績を伸ばし、大きく成長していくための第一歩になるはずです。