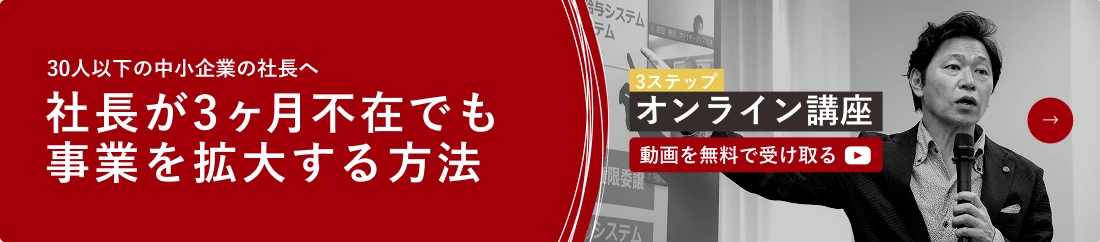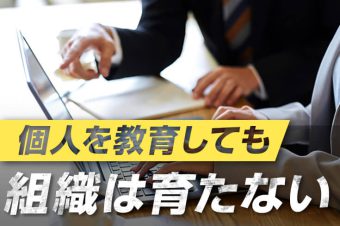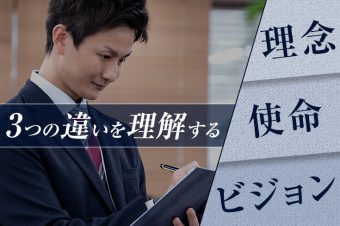- TOP
- ブログ&YouTube
- 意図を汲める社員と汲めない社員の違い


意図を汲める社員と汲めない社員の違い
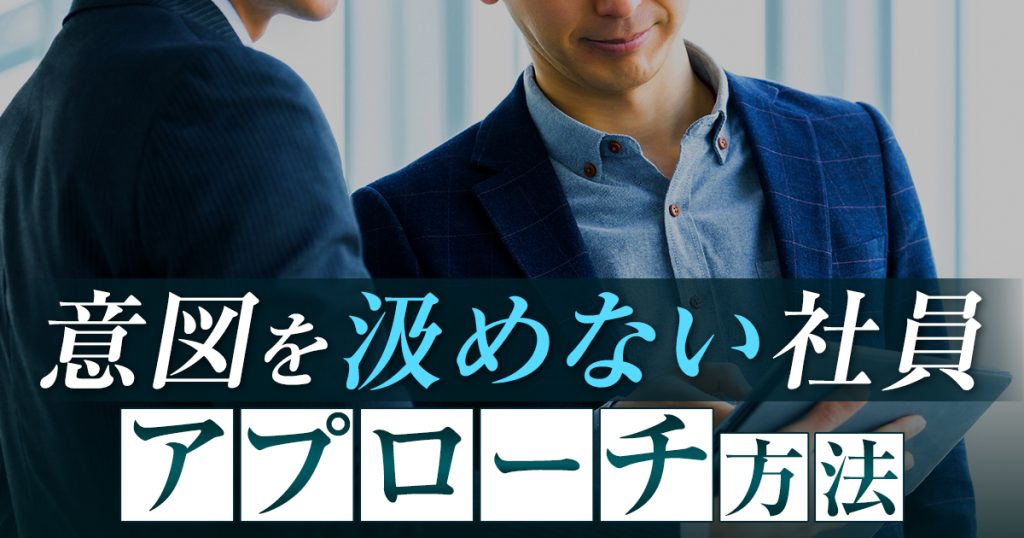
今回のテーマは「意図を汲める社員と汲めない社員の違い」です。
先日、経営者の方から”指示したことしかできない社員”についてご相談をいただきました。
「弊社の社員は、良くも悪くも素直です。指示したことは『はい!』と笑顔で頑張ってくれるものの、それ以上の動きはありません。一からすべて私が説明しなければならないのかと思うと、正直なところ苦痛に感じます。できればこちらの意図を汲んで動いてほしいのですが、どうすればそのような社員を育てられるでしょうか」
こうしたお悩みを抱える経営者は少なくありません。弊社のクライアントにもまた、「社員に自主性がない」「言われたことしかしない」と嘆く経営者が幾人もおられます。
日々組織のために忙しく駆け回っている経営者としては、「いちいち細かく説明しなくても、意図を汲みとって自力で動いてほしい」と感じますよね。しかし、これが最初からできる人は、残念ながらかなり希少といってよいでしょう。
では、意図を汲める人とそうでない人には、どのような差があるのでしょうか。今回はその違いを探りつつ、意図を汲める社員を育てる方法について考えていきます。
意図を汲める人・汲めない人の違い
初めにお伝えしたいのは「自主的に動けない=やる気や能力が低い」ではない、ということ。実は、相手の意図を汲める人とそうでない人の差は、多くの場合「話を聞く際の習慣」の違いにあるのです。
まず”意図を汲める人”は、指示を受ける際に「なぜそれを行うのか」を把握することに注力しています。指示の細かな内容よりも、その先にある目的の理解を重視しているということですね。
そして行動する際にも、指示を忠実にこなすことではなく「目的を達すること」を考える。だから、一から十まで説明されなくとも自ら動いて成果を出すことができるのです。
これに対し”意図を汲めない人”は、目的の把握よりも「相手の発言を正確に聞く」ことに注力し、「指示の内容を違えず、忠実にこなす」ことを考えて行動します。すると、「素直に頑張るのに、言われたことしかできない」という結果が生まれるのです。
目的を掴むためのアプローチ
さて、この差を解消するためには、具体的に何をすればよいのでしょうか。
単に「もっと目的を考えて」と伝えるだけでは足りません。状況を解決するためには、次のような3つのアプローチが必要です。
- 伝え方を変える
- トレーニングを行う
- 心理的安全性を確保する
まず、指示を出す際には「目的は何か」を明確に伝えることを心がけましょう。社員が自ら思考を巡らせて行動するためには、何よりも目指すゴールをしっかり共有する必要があるからです。
これに加えて、達成プロセスを考えるトレーニングも重要です。具体的には「この目的を達するために、あなたならどんな方法をとりますか」と働きかけ、出てきた案に対して「この部分は素晴らしい」「この部分は改善できる」とフィードバックを寄せる。これを繰り返しながら、少しずつ精度を上げていきましょう。
トレーニングにはかなりの手間と時間がかかるため、場合によっては適正のある社員に任せるのも手です。長期的に取り組むためには、教えるスキルに加えて気の長さも求められるでしょう。こうして適性を見極めながら役割分担を行うのも、変革を目指すためのチャレンジの一つだといえますね。
「失敗しても大丈夫」を共有しよう
そして、自主性をもって動ける社員を育てるためには、社内における心理的安全性にも着目する必要があります。なぜなら、相手の指示通り動くことに全力を注ぐ習慣は、「失敗すると責め立てられる」環境の中で身に付くことも多いためです。
間違いや失敗を糾弾される環境下では、自ら考えて動くことに対して緊張や恐怖がつきまといます。すると、いくらトレーニングを積んでも結局は「余計なことをしないよう、指示通り動くのが最適解」ということになってしまう。社員が自主性を発揮するためには「失敗しても大丈夫」という精神的な安全性が必要なのです。
これを実現するためには、失敗を責めず、挑戦を賞賛するような企業文化を築くことが大切です。たとえば弊社では、「システム思考にこだわる」「失敗にビビらずチャレンジする」「仲間を応援する」といったコア・バリューを設け、この価値観を共有することで安心してチャレンジできる文化の醸成に努めています。
本日の結論
相手の指示を聞き漏らさず忠実に実行するのは、簡単なようでいて大きなエネルギーを要することでもあります。その力を適切に使えるようになれば、「意図を汲めない」社員たちは飛躍的な成長を遂げるかもしれません。
今回ご紹介したアプローチ方法はどれも根気を要するものばかりですが、ぜひ諦めずにチャレンジしてみてください。その取り組みはきっと、貴社の新たな可能性を拓くための重要な転機になるのではないかと思います。