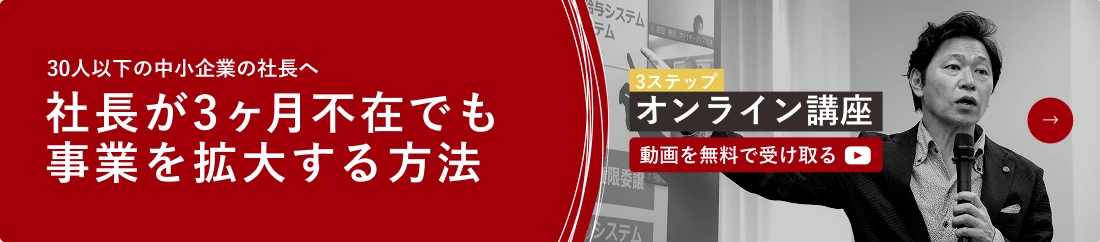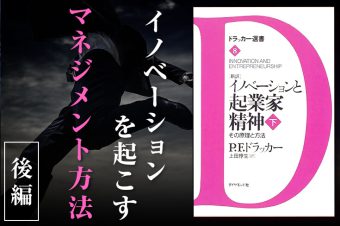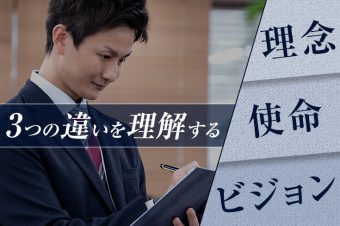- TOP
- ブログ&YouTube
- 書籍『イノベーションと起業家精神』前編


書籍『イノベーションと起業家精神』前編

今回は、書籍『イノベーションと起業家精神』(前編)を中小企業に活かす方法についてご紹介します。
著者は、現代経営学やマネジメントの父と言われるP.F.ドラッカー氏。今回ご紹介する『イノベーションと起業家精神』シリーズは、同氏の1985年の著作”イノベーションと企業家精神”の新訳版にあたります。
前後編の前編である本書では、会社をより良く変えていくために不可欠な「起業家精神」と「イノベーション」の原理が体系的に論じられています。今回は、そんな本書の内容に基づき、企業家精神・イノベーションの定義や、イノベーションを実践する方法をざっくりと解説していきます。
起業家精神とは何か
まずは、「起業家」や「起業家精神」の定義について見てみましょう。
アメリカでは、主に「新たな小規模事業を始める人」のことを「起業家」と呼びます。恐らく日本でも、似たイメージを抱く人が多いのではないでしょうか。しかし、ドラッカー氏は「新しい小さな事業の全てに、起業家精神があるわけではない」と指摘しています。
氏は本書において、「真に起業家的な事業は、新しいものや異質なものを創造する」と述べています。つまり、単に新しい事業を始めることではなく「新たなニーズの創造や、新しい方法での課題解決にチャレンジすること」が起業家精神であり、それがビジネスのイノベーションに繋がるということですね。
起業家精神を体現した企業の例としては、マクドナルドが挙げられます。
マクドナルドが提供する「ハンバーガー」自体は、アメリカの社会にとってありふれたものでした。しかし同社は、製品の標準化や製造プロセスの再設計を行い、やがては事業そのものをパッケージ化して世界中にフランチャイズ展開することで、新たな市場と顧客の創造に成功したのです。
新しいものの創造に挑む起業家精神こそがイノベーションを起こすことを、分かりやすく実感できるエピソードですね。
イノベーションの7つの機会
次に「イノベーション」の定義や、イノベーションを起こすためのチャンスの見極め方について見てみましょう。
本書では、イノベーションを「富を創造する能力を資源に与えること」や「既存の資源から得られる富の創出能力を増大させること」と定義しています。そして、イノベーションが起こる機会として、次のような7つの要素を挙げています。
①予期せぬものの生起
②ギャップの存在
③ニーズの存在
④産業構造の変化
⑤人口構造の変化
⑥認識の変化
⑦新しい知識の出現
それぞれについて、もう少し具体的に解説します。
予期せぬものの生起
予期せぬ成功や失敗を放置せず、「なぜ成功(失敗)したのか」「その気づきを活かすためにどんな取り組みが必要か」を徹底的に調査することが、イノベーションに繋がるという理論です。
ギャップの存在
業績や価値観、技術などのギャップの陰には、常にイノベーションの種があるという理論です。たとえば、私は先日「甘いイチゴが一般的ではないアメリカに、日本の”甘いイチゴを作る技術”を持ち込んだところ、爆発的にヒットした」という事例を耳にしました。まさに、国と国のギャップを活かしたイノベーションの好例といえますね。
ニーズの存在
隠れたニーズを見つけることが、イノベーションに繋がるという理論です。皆さんも、日ごろから注意深くアンテナを張っている部分ではないでしょうか。
産業構造の変化
法律の変化、新たな産業の誕生など、産業構造が変化する時期にはイノベーションも起こしやすくなるという理論です。ドラッカー氏は、「産業構造は永続・安定的なものではなく、瞬時に変化し得る不安定なものだと理解することがイノベーションに繋がる」と論じています。
人口構造の変化
人口構造が変われば、人の価値観や認識も変化する。この認識の変化を捉えることが、イノベーションに繋がるという理論です。
たとえば、かつては「収入の多さ=食事の豪華さ」だった欧米の食生活は、人口構造とともに次第に変化していきました。先述のマクドナルドのようなファストフードは、この変化を見逃さなかった結果イノベーションを起こせたともいえますね。
新しい知識の出現
新たな知識や技術の活用が、イノベーションに繋がるという理論です。たとえば現代であれば、チャットGPTのようなAI技術の活用が大きな変革を生み出すかも知れません。
本日のまとめ
私たち経営者は、新しいものの創造に挑む起業家精神を持つとともに、「イノベーションの機会」を敏感に捉える必要があります。世の中の変化にアンテナを張り、創造の可能性を真剣に模索していけば、チャンスを逃さず成功に変えることができるでしょう。
本書は、気づきをもたらしてくれるだけでなく、いち経営者として非常に心躍る内容の本でもあります。ぜひご一読になり、楽しみながら自らの視点を変えていっていただければと思います。